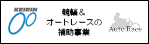Hitec newsHITEC ニュース
平成30年度「北海道新技術・新製品開発賞」開発奨励賞受賞
当センターが技術支援を行った株式会社仁光電機のゼニガタアザラシの忌避技術、株式会社イリエ船橋商店の北海道駒ケ岳の軽石を活用した魚の塩干品「北海道・鹿部 軽石干し」、ひやま漁業協同組合江差ナマコ協議会販売促進部フリーズドライナマコ「檜山海参(ヒヤマハイシェン)」が平成30年度北海道新技術・新製品開発賞(主催北海道)の開発奨励賞を受賞しました。
以下北海道ホームページより抜粋
・制度の概要
北海道では本道工業等の技術開発を促進し、新産業の創出や既存産業の高度化を図るため、平成10年から道内の中小企業者等が開発した優れた新技術・新製品に対し北海道新技術・新製品開発賞表彰を行ってきました。これまで、食品加工や機械金属などのものづくり分野で、特色ある技術や製品を表彰しています。
・表彰の対象
表彰年度の前々年度以降に開発や商品化された、新規性、独創性が高い新技術・新製品
(その一部を構成する原材料や部品、中間製品を含みます。)
■ものづくり部門 開発奨励賞■
株式会社仁光電機
ゼニガタアザラシの忌避技術
【新技術・新製品の概要、特徴】
ゼニガタアザラシが定置網に入り込んでサケを捕食する食害を防止するため、サケは逃げず、アザラシが忌避する性能を有する超音波照射技術
*****工業技術センター研究開発部ものづくり技術支援グループ村田研究主査コメント*****
本技術は、特定の周波数の超音波を用いて、サケの定置網漁に甚大な漁業被害をもたらすゼニガタアザラシ(準絶滅危惧種)に対する忌避技術です。この技術は、観光資源の希少種と水産業の共生を図る技術として、平成26年度から株式会社仁光電機、北海道立工業技術センター、東京農業大学等が連携して研究開発に取り組み、超音波周波数の特定や制御方法を検証し続け、平成29年に定置網漁での実証試験で忌避効果の可能性が認められました。この技術は、サケ漁の食害低減に寄与することで、北海道の特産物の安定確保に資するものと考えております。

(写真)超音波照射装置(環境省請負業務)
■食品部門 開発奨励賞■
株式会社イリエ船橋商店
北海道駒ケ岳の軽石を活用した魚の塩干品「北海道・鹿部 軽石干し」
【新技術・新製品の概要、特徴】
地域資源である駒ケ岳の軽石の吸水力を活用し、うま味成分を多く残すための脱水技術を用いた魚の塩干品
*****工業技術センター研究開発部食産業技術支援グループ清水研究主査コメント*****
本製品は、鹿部町の地域資源である軽石と水産物を活用した新規、且つ高品質な塩干品です。水産業が基幹産業である鹿部町には、活火山・北海道駒ケ岳から噴出された吸水性の高い軽石が豊富に存在します。「この軽石と新鮮な魚で美味しい塩干品を作れないか」という鹿部町製品開発研究会のコンセプトから「北海道・鹿部 軽石干し」が誕生しました。本製品の特徴は、①魚を吸水性の高い軽石に埋めることで脱水した他に例のない塩干品というだけではなく、さらに、②鮮度低下と伴に減少する旨味成分「イノシン酸」を多く残すための工夫として、冷蔵(5℃以下)、且つ短時間(一日以内)での脱水技術を確立して開発された塩干品です。開発にあたっては、北海道立工業技術センターが有する技術開発力、鹿部町製品開発研究会の企画力、Royal Hotelみなみ北海道鹿部料理長等による評価力が生かされています。

(写真)北海道・鹿部 軽石干しのホッケ、ソウハチ、イワシ
■食品部門 開発奨励賞■
ひやま漁業協同組合 江差ナマコ協議会販売促進部
フリーズドライナマコ「檜山海参(ヒヤマハイシェン)」
【新技術・新製品の概要、特徴】
干しナマコの製造を従来の天日乾燥から凍結乾燥に変更することで、成分変化を極力抑制した新しいナマコ製品
***** 工業技術センター 研究開発部 応用技術支援グループ 小西研究主幹コメント *****
本製品は、北海道内でも高品質なことが知られている江差産ナマコを用い、フリーズドライ(FD)製法を用いた国内初の乾燥ナマコです。乾燥ナマコの新たなニーズや付加価値向上を目的に開発製品に取り組み、FD製法を用いることにより乾燥品の見た目の大きさが大きいこと、復水時間が従来・天日乾燥ナマコに較べ大幅に短時間化することが特徴です。このフリーズドライナマコは、これまでの乾燥ナマコを用いている中華料理のシェフから高い評価を得ていますが、まだナマコを使ったことのないフレンチやイタリアンのシェフからも洋食に使えるとの評価を得ています。乾燥品の大きさが大きいことから、東南アジアからのインバウンドの旅行客からも大変注目されており、まずはそれら旅行客に向けたお土産品として商品化・販売を開始しています。良質な素材と新たな発想・技術を取り入れた北海道を代表する海外に向けた水産加工品になることを期待しています。

(写真左)「フリーズドライナマコ」
(写真右)「檜山海参(ヒヤマハイシェン)」製品例

(写真)受賞された方々

(写真左より) 工業技術センター村田研究主査
株式会社仁光電機代表取締役柏谷和仁氏
辻泰弘副知事
株式会社イリエ船橋商店代表取締役船橋敦子氏
工業技術センター清水研究主査
工業技術センター阿部副センター長
工業技術センター見学の申し込みを随時受け付けしております。
皆様、お気軽に見学にいらしてください。

(写真)北海道立工業技術センター展示ホール
※共同研究・技術相談成果品等多数展示しております。
【お問い合わせ】公益財団法人函館地域産業振興財団 研究開発部研究支援課
℡(0138)34-2600
※6月から8月迄は、下記の方々がセンターを見学にいらっしゃいました。
・北斗市高齢者大学 北斗市浜分ふれあい大学 様
・北斗市高齢者大学 北斗市きらめき大学 様
・北海道函館工業高校工業化学科 様
・渡島総合振興局 インターシップ研修生 様
・上海海洋大学、岩手大学、北海道大学 様
・カセサート大学、フアジョン農業大学、北海道大学 様
・静岡県経済部 様
 (写真左)北斗市高齢者大学の皆さん
(写真左)北斗市高齢者大学の皆さん
(写真右)函館工業高等学校の生徒さん

(写真左)上海海洋大学、岩手大学、北海道大学の学生さん
(写真右)カセサート大学、フアジョン農業大学、北海道大学の学生さん
工業技術センターでは個別技術研修を行っています。
企業などの技術的課題の多様化に対応するため、個別密着型で、かつ技術移転を重視した個別の技術研修を行っております。食品の加工・品質評価、工業材料・部品等の試作・評価、測定・試験用機器の活用方法など個々の技術ニーズに対応いたしております。
【開催日】随時
【場 所】北海道立工業技術センター
【受講料】無料
【お問い合わせ】公益財団法人函館地域産業振興財団 工業技術センター研究開発部
℡(0138)34-2600
「平成29年度北海道立工業技術センター業務報告」が完成
北海道立工業技術センターの平成29年度の活動状況をまとめた「北海道立工業技術センター業務報告」ができました。ご希望の方はご連絡ください。無料で提供しています。
【お問い合わせ】公益財団法人函館地域産業振興財団 研究開発部研究支援課 ℡(0138)34-2600
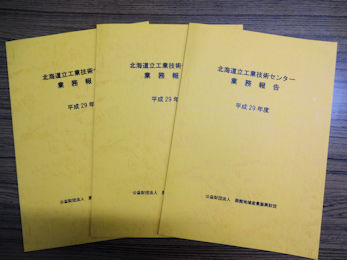
(写真)平成29年度北海道立工業技術センター業務報告
2017年度(第56期)日本伝熱学会技術賞受賞
当センター、研究開発部食産業技術支援グループ吉岡研究主幹が鮮度保持の実証等に係わった「小型漁船搭載型の製氷機による漁獲物鮮度保持用シャーベット状海水氷の大量製造技術」が日本伝熱学会技術賞を受賞しました。

(写真)小型漁船搭載型製氷機「海氷」
【受賞件名】小型漁船搭載型の製氷機による漁活仏鮮度保持用シャーベット状海水氷の大量製造技術
【受賞者】 佐藤 厚 (株)ニッコー
輪嶋 史 (株)ニッコー
千葉繁生 (株)ニッコー
藤原隆弘 (株)ニッコー
山川健太 (株)ニッコー
稲田孝明 産業技術総合研究所
永石博志 産業技術総合研究所
吉岡武也 北海道立工業技術センター
【表彰式】 日 時:平成30年5月30日(水)16時45分~18時15分
場 所:札幌コンベンションセンター 大ホールA

(写真)日本伝熱学会技術賞を受賞した吉岡研究主幹
***以下公益社団法人日本伝熱学会ホームページより抜粋***
【公益社団法人日本伝熱学会・概要】
日本伝熱学会は、伝熱に関する学理技術の進展と知識の普及、会員相互及び国際的な交流を図ることを目的としている学術団体です。会員数は約1500名であり、機械工学、化学工学、原子力工学、冷凍空調、バイオエンジニアリング、食品工学、建築学、地球科学など幅広い学術分野にわたる科学者や技術者で構成されています。そのため本会の学術的活動は広範囲に及び、由緒ある伝統を確立する一方で、伝熱工学にかかわる海外に開かれた組織として発展してきており、国籍や人種にかかわりなく、いかなる研究者も会員になることができます。本会は、伝熱研究にかかわる研究者や技術者間の情報交換を促進するために、1961年に全国的な同学の士が集まり作られた研究組織を母体としています。会員相互の親しみのある雰囲気により長期にわたって積極的な活動を維持してきています。
・技術賞の対象は、公表された優秀な伝熱技術を開発した者とします。
工業技術センター見学の申し込みを随時受け付けしております。
皆様、お気軽に見学にいらしてください。

(写真)北海道立工業技術センター展示ホール
※共同研究・技術相談成果品等多数展示しております。
【お問い合わせ】公益財団法人函館地域産業振興財団 研究開発部研究支援課
℡(0138)34-2600
工業技術センターでは個別技術研修を行っています。
企業などの技術的課題の多様化に対応するため、個別密着型で、かつ技術移転を重視した個別の技術研修を行っております。食品の加工・品質評価、工業材料・部品等の試作・評価、測定・試験用機器の活用方法など個々の技術ニーズに対応いたしております。
【開催日】随時
【場 所】北海道立工業技術センター
【受講料】無料
【お問い合わせ】公益財団法人函館地域産業振興財団 工業技術センター研究開発部
℡(0138)34-2600
「平成29年度北海道立工業技術センター業務報告」が完成
北海道立工業技術センターの平成29年度の活動状況をまとめた「北海道立工業技術センター業務報告」ができました。ご希望の方はご連絡ください。無料で提供しています。
【お問い合わせ】公益財団法人函館地域産業振興財団 研究開発部研究支援課
℡(0138)34-2600
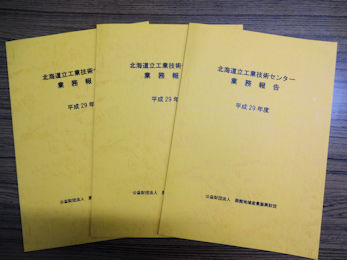
(写真)平成29年度北海道立工業技術センター業務報告
平成30年度北海道立工業技術センター研究成果発表会開催
日 時:平成30年5月17日(木)13:30~17:00
場 所:フォーポイントバイシェラトン函館
参加者:167名
5月17日(木)フォーポイントバイシェラトン函館において工業技術センター研究成果発表会を開催しました。三浦センター長の開会挨拶に続き、企業や大学との共同研究などの成果8題を発表しました。発表会では、同時に「昆布たっぷりのだし粉」を使った試食品、春採り真昆布スティック、こんぶの酢の物の試食や定置網漁向けアザラシ用忌避装置(レプリカ)、昆布毛取り機の展示や(地独)北海道立総合研究機構 食品加工研究センターの「ホタテ外套膜を原料としたスナック及び調味料の開発」に関するポスターの展示を行いました。来場の皆様からは多くの質問や貴重な意見が寄せられ、今後の研究開発に生かされることが期待されます。引き続き開催した交流会にも、多数の皆様にご参加いただき、活発な情報交換が行われるなど、研究成果発表会は盛会裏に終了しました。
*****研究成果発表会プログラム*****
1.ゼニガタアザラシの忌避装置に関する実験的検証
村田政隆(ものづくり技術支援グループ)、井筒慶汰(株式会社仁光電機)
一昨年度、希少種であるゼニガタアザラシによる定置網漁の食害低減を図るには、超音波が有効であるとの検証結果を報告した。今年度は、忌避技術の装置化および実際の定置網で実施した忌避効果の検証結果等について進捗報告した。
2.マスク型ワイヤレス呼吸リハビリ・トレーニングシステムの要素技術開発
松本陽斗(ものづくり技術支援グループ)
呼吸機能改善や運動能力向上等には呼吸法のトレーニングが有効であり、その指標となる呼吸量を簡便に測定できる機器が求められている。本発表では、呼吸トレーニングマスク “ReBNA”用ワイヤレス呼吸量センサの各種技術開発及び検証内容について報告した。
3. 函館真昆布の美味しさを活かした「だし関連製品」の開発と商品化の取り組み
小西靖之(応用技術支援グループ)
函館真昆布を活用した製品開発を行い、「だしパック」や「だし醤油の素」、「だしオイル」など技術開発・技術公開を行い製品化に取り組んだ。またロゴマークの制作、研究会の設立、展示会等での販売促進なども行った。これらの取り組みの概要を紹介した。
4.プラズマ灯を用いた低消費電力型イカ釣り漁灯の開発
高橋志郎(応用技術支援グループ)、柏谷和仁(株式会社仁光電機)
高輝度で高演色性、発光部のサイズが極めて小さく、配光制御が容易であるプラズマ灯を用いて、一次産業用途を目的とした灯具の開発を行った。本発表では、函館の主力漁業であるイカ釣り用の漁灯開発について、当センターの取り組みを中心に紹介した。
5.北海道駒ヶ岳の軽石を活用した魚の塩干加工品「軽石干し」の開発と商品化
~鹿部町の資源で新たな特産品を目指して~
清水健志(食産業技術支援グループ)、鈴木昌志(鹿部町製品開発研究会)
北海道駒ヶ岳の麓に位置する鹿部町には、過去の火山噴火で堆積した吸水性の高い軽石が豊富に存在する。本発表では、この軽石を活用した塩干加工品「軽石干し」の開発と商品化について、鹿部町製品開発研究会と取り組みを紹介した。
6.海藻が有する新たな食品科学的機能の探索
~コンブの粘りが味の持続性に及ぼす影響~
木下康宣(食産業技術支援グループ)
コンブはこれまで、芳醇な旨味を有するが故に「美味しさ」を最大の価値とする利用がなされてきた。しかし、今後は新たな特性を探り、「健康に寄与する美味しさ」へと変換を図ることも重要である。本発表では、最近の研究で分かってきた呈味性保持機能を紹介した。
7.ダッタンソバ道産品種「満天きらり」の食品加工におけるルチン・ケルセチン含量調節法の
開発とその食品機能性
大坪雅史(食産業技術支援グループ)
ダッタンソバ道産品種「満天きらり」は、苦みが少なくルチン分解酵素活性が低いためルチンを豊富に含む食品を製造できることを特長とする。我々は、演題の調節法を開発し、ルチン・ケルセチンの各々の食品機能性を標的とする食品加工の可能性を見出した。
8.スラリーアイスを用いた北海道産鮮魚の高鮮度流通
吉岡武也(食産業技術支援グループ)
スラリーアイスは魚を急速に冷却するほかに、鮮度保持に有効なスーパーチリング温度帯を安定して維持する機能もある。スラリーアイスを利用して、北海道産の鮮魚を高鮮度で海外などに輸送する取り組みを紹介した。

(写真左)研究成果発表会の様子
(写真右)鹿部町製品開発研究会 鈴木昌志氏(右)と工業技術センター研究主査 清水健志

(写真)試食・展示の様子
工業技術センター見学の申し込みを随時受け付けしております。
皆様、お気軽に見学にいらしてください。

(写真)北海道立工業技術センター展示ホール
※共同研究・技術相談成果品等多数展示しております。
【お問い合わせ】公益財団法人函館地域産業振興財団 研究開発部研究支援課
℡(0138)34-2600
- 只今、工業技術センターの改修工事を行っており、見学できない期間がありますので、ご注意下さい。詳しくは研究開発部研究支援課にお問い合わせ下さい。